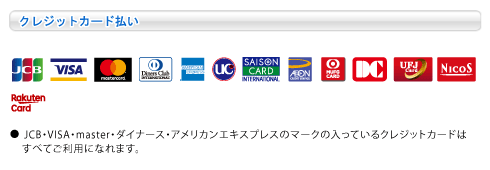- ホーム
- 特徴と独自技法
三川内焼の技法
平戸洸祥団右ヱ門窯では、三川内焼の薄さや佐世保市無形文化財指定「平戸菊花飾細工技法(ひらどきっかかざりさいくぎほう)」、平戸置上技法(ひらどおきあげぎほう)、繊細な染付といった伝統技法を大切にしながら、よりよい作品づくりに励んでいます。
また、明治、大正、昭和と当窯に伝わってきた美しい意匠をすべて見直し、現代に十分通用する卓越した器を選び、その再現に取り組んでいます。代表的な技法について、ご紹介します。

三川内焼では、熊本県天草で採れる天草陶石を使用します。この天草陶石が、白さのもとです。原石は、専用の機械を用いて、粉状になるまで一日かけて細かく砕いていきます。


ろくろや手などを使って成形していきます。成形は、焼き物の形を決定づける重要な場面です。さらに、成形の段階で、置物などに仕上げていく場合は、様々な技法を使って形をつくっていきます。





天日によって乾かしたら、本焼きに入る前に900度の高温で7時間ほど素焼きを行います。素焼きを行うのは、この後の工程である絵付けをするためです。


「骨描き」では顔料の呉須(ごす)を筆を使って丁寧に絵を描いていきます。呉須は、下絵の段階では灰色ですが、焼きあがると鮮やかな青になる不思議な染料です。


骨描きをした後に、太い筆にたっぷりと水でうすくといた呉須(顔料)をふくませて「流し濃み」(ながしだみ)という技法で色をつけていきます。流し濃みでは、生地表面を筆先でこすらずに色付けできるために、筆むらが残らずに色を染めこませることが可能です。


下絵を施した後は、釉薬(ゆうやく)という薬を全体にかけていきます。この釉薬を施すことによって、ガラスのような透明感がうまれ、強度もしっかりとしてくるのです。


高温の1300度ほどまで温度を徐々に高めて、15時間ほどかけて焼成します。当窯では、高い1300度を保って焼成しますので、より強度の高い作品を焼成することが可能です。

染付技法

およそ900度で素焼きした素地に、藍色の絵具・呉須(ごす/顔料のコバルト)を含ませた筆で絵や文様を描き、着色する技法です。
まず、絵柄の輪郭を描く「骨描き(また下絵付け)」を行い、次に、絵柄に色を塗る「濃み(だみ)」という行程に進みます。
専用の太い濃み筆にたっぷりと呉須を含ませ、表面に流すように染み込ませていきます。
当窯では、中里閑由(なかざとかんゆ)と幸美(ゆきみ)が絵付けを、職人1人が濃みを行う体制を取っています。
同じ染付でも、産地によって絵付けや濃みの方法は異なります。




焼成(ガス窯と登窯)


焼成には酸化焼成と還元焼成の2種類があり、当窯では用途に応じ、ガス窯2基と電気窯1基を使い分けています。
素焼きには主に酸化焼成のできる電気窯、本焼には還元焼成のできるガス窯で焼いていきます。
当窯が器の原料とする天草陶石(あまくさとうせき)は、還元焼成を行って初めて、白くなります。
還元焼成は窯の中で酸素が少ない状態で温度を上げる方法で、釉(うわぐすり)のなかの酸素が奪われて透明から青みを帯びていくことで、器が白くなるのです。
ガス窯は大体2時間おきに温度と燃料となるガスの量をチェック・調整して、15時間ほどで1300度に達します。そして、窯の火を止め、1日かけて窯内部を冷まします。
これが登窯になると、窯に交代で燃料となる薪を入れ続け、2日もしくはそれ以上の時間をかけて窯を焚き、さらに冷ます時間が必要となるのです。
ガス窯の方が登窯にくらべ熱効率がよく、同じ作品が同じ質で焼けるため、磁器を制作している窯元はガス窯の利用が一般的です。

三川内では登窯を日常的に使用している窯元はありませんが、年に1〜2度 共同で制作した登窯で作品を焼成することがあります。
登窯には計算通りにいかない不安定さがありますが、そのことがガスや電気の窯がなかった江戸時代を彷彿(ほうふつ)とさせる肌合いや、予想のできない仕上がりになるからです。これは自然の力を利用した焼成法でしかなしえないことで、作品がそれを物語っています。
私どもの工房は1955(昭和30)年頃まで登窯のあった場所で、増改築をくり返し、2001(平成13)年11月の改築を経て、現在の姿になりました。